姿勢改善の全てをここに!
前回のブログより、姿勢改善についてのお話をさせていただいております。

姿勢改善アプローチの変遷ということで、15年ほど前までは筋肉の長い・短いに対するアプローチが行われ、10年ほど前まではそのアプローチに加え、機能的連鎖に対するアプローチが行われ、そして5年ほど前から現在に至るまでは神経系や感覚器、内臓、栄養に対するアプローチへと変わっていっているということをお話いたしました。
今回は、そうした考え方の変化を踏まえた上で、実際にどのようなプロセスを経て我々の姿勢が成り立っているのかということを詳しく見ていきたいと思います!
まず、脳神経系の機能不全が起こることで組織の伸長性の問題や関節の機能不全が発生することで「不良姿勢」は出来上がります。
このようなことを考えた時に、よく行われるマッサージやリリースといった対症療法のみならず、根本的な神経系への介入が必要となります。
ここで具体例を見ていきたいと思います。例えば右側の巻き肩を改善しようと考えた時に、その原因として同側(右側)の脳幹網様体の活性不全・機能不全が挙げられます。
脳幹網様体とは、脳幹(中脳・橋・延髄)にある神経繊維が豊富な網目状になっている部分で筋緊張や覚醒レベル、自律神経系の活性や痛みの感知など様々な身体活動に関与するところとなっています。
他にも、脳幹網様体と深い関わりのある同側(右側)大脳皮質の活性も重要となります。
しかし、従来のアプローチでは「右が巻き肩なので右の大胸筋をリリースする」となります。
実は右から入力された感覚は、右の小能、そして左の大脳皮質や脳幹を活性化するのです。つまり、根本である右側の脳幹網様体、そして大脳皮質の活性化は達成されないのです。
ただ、こうしたリリースやストレッチが意味ないかと言われるとそういうわけではありません。
1b抑制というゴルジ腱器官による筋緊張抑制というような末梢のアプローチによる対症療法的な効果は期待できるのです。
以上のように、姿勢改善を目指す際は筋肉の短長のみならず、根本である脳へのアプローチが必要となるのです!
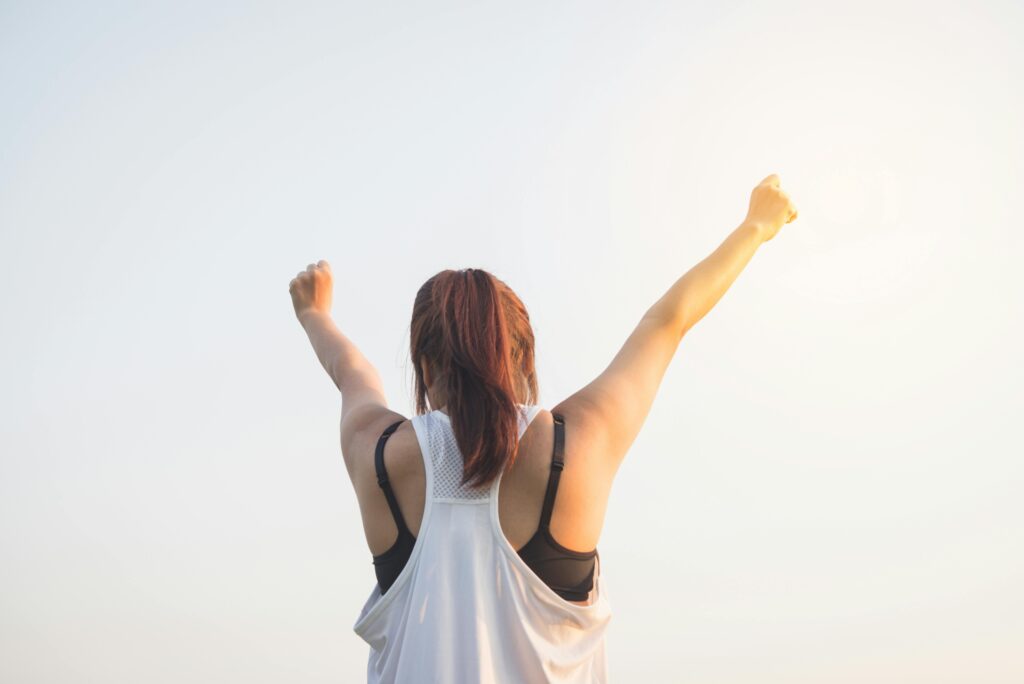

コメント